�V�m�v�V�X�Aetc�̃y�[�W�ł�
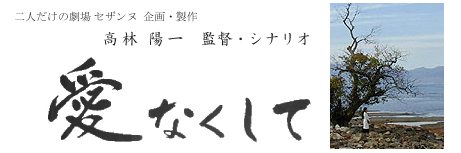 |
| �u���Ȃ����āv�p���t���b�g��蔲���@�@ |
|---|
| �����Ȋ�ց@�i���_�����̔��W������āj �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�v�m�q �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�f��u���Ȃ����āv�����l�����̌���Z�U���k��Ɂj �@�V���o�D�Ƃ��ē��X�����̔Y�݂��������Ȃ���i���c�ێ��E�����ꓙ�X�j�A����ł��ǂ���i���Y�ݏo�����������Ƃ����ꖕ�̖������ɔ��1999�N8��1���A�E�C���N���A�u�����f����B�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v�ƁA����������Ă���ꂽ���їz��ēɂ�����邱�Ƃɂ����B8�����z�̃W���W���Ƃ���钆�A�����ɂ��߂����肢�������ɔ�߁A���쉈���̓y��A���̎v���͓`���̂ł��낤���H�����Ɍ��݂̎��̐S������b���Ȃ���E�E�E�B�ߌ�1�����s���C�����z�e���i�����ɂċv���Ԃ�ɍ��їz��ēɂ�����邱�ƂɂȂ�B�u���Ŗ����Ȃ���R�c�R�c�Ɛ������w�����������葱���Ă���l�B�����܂��B����͈�u�̂����ɏ����ĂȂ��Ȃ鐢�E�ł��B�ł����牽�����������̂ƐM���Ă��܂����A��삭�炢�f���Ɏc���i�������Ă��ǂ��ƍl���Ă��܂����A���V���o�D�̎p���ǂ����Ă��f���ɂƂǂ߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B�S�����K�I�]�T�͂���܂��Ȃ�Ƃ��F����ɂ��肢���Ď����������ƍl���Ă���܂��B�v�Â��Ȍ����Ŋē̌��t���������ꂽ�B�u�ǂ�ȓ��e�̍�i���Ƃ��l���ł����H�v�u�����̑����E�l�Ԃ̐��Ǝ��ɂ��Ăӂꂽ��i��ɖ]��ł��܂��B�v���X�B2���ԋ߂��̉�b�̂��Ƃ�̌�A�f����B���Ă��������� ���邱�Ƃ��ł����B���ɂƂ��Ė��̂悤�ȁA�v���������Ȃ��o�����A�����Ȋ�ւ̎n�܂�ł���B������ē̓V�i���I�쐬��Ƃɓ��邱�ƂɂȂ�A���͐���Ďn�߂Ă̌o���f�搻��҂Ƃ��Ă̋�̓I�Ȋ����ɓ��邱�ƂɂȂ�B���E�E�E�A�E�C���N�����ēɂ��肢�ɂ����������̂́A�V���o�D�Ƃ��Ă̂݊����𑱂��Ă������ɂƂ��ĉf�搻��͂܂��������m�̐��E�ł���B�{���ɐ����B�ł���̂ł��낤���H���ɏo�����Ă��������o�D����B���F�n�R�邵�ł���B���͒P�ɖ���ǂ������A�ē⋦�͂����ĉ�������X�ɂ���J�����|�����邱�Ƃ����ɏI���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���ƕs���Ȗ邪�������A�R�c�R�c�Ɖf�搻��̏����Ɏ��|�������B�܂���l�����̌���Z�U���k�ϋq�̊F����ɉf�搻��̂��߂̕���̂��肢���n�߁A���Ɉ�ʂ̕��X����������邱�Ƃɂ����B���ъēɊւ��Ă͓������{�����e�B�A�ɂĎQ�����Ă��������Ƃ����L�������t�����������A�o���҂Ɋւ��Ă��S���{�����e�B�A�Q���̏����邱�Ƃ��ł����B���X�ɉ����������n�߂Ă���B�u�f��삷��Ƃ������Ƃ͐g�̂ɍY��ł����ނ悤�Ȃ��̂ł���B�v�Ƃ���v���f���[�T�[�̌��t���v���������B���̋�J�Ȃ�Ĕ��X������̂ł���A��̂��Ƃ��l�� ��O�ɍ��ł��邱�Ƃ���n�߂悤�Ǝ����Ɍ�������������X�ł���B2001�N12���V�i���I�����A2002�N1���V�i���I�W�҂ɔz�z�B2���E3���V�i���I���n�[�T���B2002�N4�����悢��Җ]�̎B�e�J�n�ł���i�B�e�Ɋւ��Ă̓[�U���k�z�[���y�[�Whttp://www.gocities.jp/cezanne1983/�A���Ȃ����ĎB�e�����ɏڂ����L���Ă���j������2003�N3��20���҂��ɑ҂����������ʂ��}���邱�Ƃ��ł����B���ɂƂ��ď����ȏ����ȁA�����đ傫�ȑ傫�Ȋ�ւł���B �@�������ʂ��}����ɂ������Ă�3�N���̍Ό��A�Z�U���k�ϋq�̊F�l�A��ʂ̊F�l�A�F�l�E�m�l���v�����������g������܂��̂����t��Y����ꂽ���z�̕���ՁB���їz��ēA�B�e�ēƂ��������������y�уX�^�b�t�̕��X�A�o���҂̊F����̕��X�Ȃ�ʋ��́A�e���ʂ̊F�l�̎B�e���́A��`���́A���їz��v���_�N�V�����A���[�r�[���[�N�V���b�v�A�r�W���A���A�[�c���w�Z���싦�͂�2003�N3���A���їz��r�{�E�ēf��u���Ȃ����āv�͊��������B�����ĉf��u���Ȃ����āv�̊����͎��̐l���ɂƂ��Ĉ̑�ȓN�w���ƂȂ莄�B�̐S�̕�ƂȂ�B�l�͎x���̖_������n�߂Đ��藧�B�l�͈�l�ł͉����Ȃ����Ȃ����ƁA�����ɓ����ӎu�������Ԃ��݂�A��܂��̌��t���݂�A�v�����̍s�ׂ��݂�A�l��M����͂��݂�B���Ƃ������̂��̂��l���ɉ������u�̏u�Ԃł���ɂ���A���̏u�Ԃ���͂�^���ĉ������܂��������̊F�l�̎x���̂��S���ɍ�����������E�E���_���E�̔��B���肢���ݑ����ĎQ��܂��B ��R�̌䋦�͂�S�����\���グ�܂��B ���с@�z�� �@2000�N8��1���ߌ�3���A���s���C�����z�e��1�K�̃R�[�q�[���E���W�ŁA���͐V�����D�ŁA�����Ɂu���c��l�����̌���Z�U���k�v�̎�Ɏ҂ł�����A�����v�m�q����ƈ������B���̎��A��������̌�����o�����t�́A�u���c�ʼnf���n�肽���̂ł����A�䋦�͊肦�܂����v�Ƃ����悤�Ȏ�|�̎��ł������B�ˑR�̂��ƂɁA���͂ǂ��Ԏ������Ă������̂��A�����̒��ŁA���t��T���Ă����B��������Ɖ]���A��B�̍��Z�𑲋Ƃ���Ɠ����ɁA���˂Ă��̊�]�ł������V���̏��D��ڂ����ċ��s�֏o�ė��āA�f��ēł�����������o������ɂ��錀�c�u���݂���v�ɏ����A���ꂪ�X�^�[�g�ŁA���̌�A�Ɨ����āA���j �[�N�ȏ��D�Ƃ��āA���܂��܂ȉ������������ė����l�ł���B���̐l���A�����̌��c�ʼnf���n�肽���Ƃ����B�F�X�A�b�����Ă������ɉ������A�u���ł͋�J���Ȃ���n���Ɋ������Ă�����҂���R�����܂��B���̐l�B�̎p���f���ɂ��ĂƂǂ߂Ă��������̂ł��v�ƁA����ꂽ�B���͂��̌��t�ɁA�������狹�ɔM�����̂��A���݂����ė���̂������āA���̘b�ɂ͖������ŋ��͂��悤�Ǝv�����B��������̒��ɂ���A�M���v�����A���ɂ��`����ė����̂ł���B�����̂��߂ł��Ȃ��A�c���̂��߂ł��Ȃ��A�����̂��߂ł��Ȃ��f������B����͉�������20�N�O����A���s�̉~�R�����̂�������O�ŁA����1��A�����ė���ꂽ��O�������x���Ă��鉓������̕\�������ɑ����M�Ɠ����́A��������łȂ���Ώo�ė��Ȃ����z�ł���B���͋v���Ԃ�ɁA���̒��ɂ܂��c��̂悤�Ɏc���Ă���A�f��ւ̑z�����A��݂������ė���̂��������B1986�N�ɁA�u���V�с@�ق������v�Ƃ����f����B���Ĉȗ��A���͉f����B���Ă��Ȃ��B15�N�Ԃ̊ԁA���͎����̒��Ɂg�f����B�肽���h�Ƃ����z�����A���̂����ĂȂ������B���ꂾ���u���V�с@�ق������v�Ƃ����f��́A���̒��́g�f��ւ̑z���h���[�����Ă��ꂽ�̂�������Ȃ��B���̎��̉f��́A�����B�낤�Ƃ����A���́A�Ƃ��߂��ɂ������f��ւ̑z���B���́A�����v�m�q����Ƙb���d�˂邤���ɁA���̑z������݂������ė���̂������Ă����B���ɂ��A���̉f�悪�������̂ł���B�������āu���Ȃ����āv�͎n�܂����B�����A���̎��A���������̈ꌾ������Ȃ���A���͉��Ƃ�����Ƃ��������������āA���̉f������A���f�肵�Ă��������m��Ȃ��B��������̒��ɂ���A�M���v�������̉f��ւ̔M���v�����Ăт��܂����̂��B�u��J���Ȃ���n���Ɋ������Ă�����҂����v�̎p�������A�����̉f��ɎB�肽���Ǝv�����̂ł���B�����A���߂ĉ�������̕���������̂́A1985�N2��9���A���s�̃n�C�h���Ƃ����i���X�ŁA�n�C�h���T�^�f�[�V�A�^�[�Ƃ����������������A���̎��ł���B���̍��́A�������u�O�l�̉�v�Ƃ������c�ł������B���̗��N��1986�N��4���Ɂu�Ǐ��v�Ƃ�������������Ă�������B���̍�����A���݂Ɏ���܂łɋ��ɕ��������ė���ꂽ�A�l�薞�i���F���g�j����́u�R���v���������ɕ���ŗ��āA���̍����猀�c�����u��l�����̌���v�Ɖ��߂��B���̖����͍�Ƃ̓��{�`�ꎁ���ƕ����Ă���B�����Ď����1983�N�ȗ��A�~�R�����̖�O�������������āA�{���Ƀ��j�[�N�ȁA���������ɐ����ė����{���̉����l�ł���B���́A����܂ʑn�����_�ɐG��Ȃ���A���́u���Ȃ����āv�͍���Ă��Ȃ��������낤�B�l���Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ŁA�����̐l�Ɛڂ��A�����������A�������ɗF�l�Ƃ��ĔF�߂Ă��Ă��A1�̔M���v�������L����l�Ƃ����̂͋H�ł���B�����v�m�q����Ǝ��́A����܂ł͏��D�Ɗϋq�Ƃ����W�ɉ߂��Ȃ������B�������鉓������́A����ʼn�����\�����Ă���P�l�̏��D����ł����Ȃ������B����ȊO�̏ꏊ�ŁA�������Ĉ����̂́A���̎����n�߂Ăł������B�����Ă��̓����́A��������̂��̉f��ɑ���M���v�����A���L���邱�ƂŁA�P�̐��E��n�삷�邱�Ƃ��o�����̂ł���B�f��u���Ȃ����āv�́A�������āA���̒��ŐV�����f��Ƃ��Ẳ���R�₵�n�߂��B�ڂ݂�A50�N�̉f��l���ł���B�������̉f��́A5�{�̍�i�������ẮA�����őn�肽������n��Ƃ����A�����鎩�吻�삩�A����ɋ߂��f��ł������B������A��ی�y�Ƃ��āA���Ζׂ���f��A�����鏤�Ɖf��Ƃ��č�������̂ł͂Ȃ��A�ނ����Ƃ��L�����o�X�Ɏ��R�ȐF��h��悤�ɖ��A���l�������̎v�������R�Ɏ��ɏ����悤�ɁA�f���Ŏ����g�̓����ɂ���A���܂��܂ȃC���[�W��\�����ė������̂ł���B�l�́A����������f��Ɖ]���A���A�O�q�f��Ɖ]���A���ɂ̓A���_�[�O���E���h�f��ƌĂB�ϋq���ӎ����č�邱�Ƃ��A�܂��������g�̕\�������Ƃ��Đ��삷��B�ɒ[�Ȍ�����������Ύ������g�̂��߂ɍ��Ƃ����Ă������A����ȉf�悪���������B�����A�\���̖{���Ƃ������̂́A�����������̂ł���B�N���̂��߂ɂ�����̂ł͂Ȃ��A�܂��A�������g�̂��߂ɁA�ǂ�Ȕ}�́i��ި��j�ł����݂���̂ł͂Ȃ����낤���B�f��u���Ȃ����āv�����A�����������̒��N�̉f��̗���̒��őn�����f��ł���B���͍��N72�˂ɂȂ����B72�˂ɂ�72�˂̃C�����[�W����������B����́u���v�̃C�����[�W�������B���{�̒j���̕��ώ�����78�˂��Ƃ����B���ώ����܂Ő������Ƃ��Ă��A��A6�N�ł���B�����āA���̊Ԍ��N�Ōܑ̖����ł����邩�ǂ����A�킩��Ȃ��B�F��Ȃ��Ƃ��v�����ŁA�u���v�ɂ��čl���邱�Ƃ������Ȃ����B���͂��̉f��̒��ŁA�����̎��ɂ��Č�肽���Ǝv�����B���ꂪ�A�����̉f�����鎄�̎��R�Ȑ��_�̌���Ƃ��Č����Ă�������Ǝv�����B�l��������Ƃ������Ƃ́A�P���P���A���Ɍ����čs�����Ƃł�����B�ǂ�ȂɎႭ�Ă����͊m���ɑ��݂��Ă���B��������A���ۂ��Ă��A����͐l�Ԃł���ȏ�A�s�\�Ȃ��Ƃł���B�u�l�͉��̎��ʁv�A���̉i���̖₢�����ɓ�����ɂ́A���͎��̍��̐S��œ��g��̉f�������葼�ɕ��@�͂Ȃ������B20��ɂ�20��̃C�����[�W����������B�����ɂ͋��炭�u���v�̂�������Ȃ��ł��낤�B30��.40��A50��A60��Ƃ��܌ڂ݂āA���Â��v�����Ƃ́u���̐����ė���70�N���āA��̉��������̂��낤�v�Ƃ������Ƃł���B������20��̎��A������70�˂ɂȂ邱�ƂȂǑz�����o���Ȃ������B�f����Ɉꐶ�����ɂȂ�A�����������A�f��A�f��Ɩ������Ă������̓��X�A�������₪��70�˂ɂȂ�ȂǂƂ́A�l�������Ȃ������B�l���Ƃ͎c���Ȃ��̂��B���ɂ���Ĉ�����҂�D���A�l���ǓƂ̕��ɒǂ����B�C������72�˂ł���B�l���ł͓�����̂��������A�������̂������Ƒ����B�m��ʊԂɎ��͂���N�����Ȃ��Ȃ��đ��P�l�Ƃ������Ƃ�����B���́A���̉f��ŁA�̋����n�߁A���܂��܂Ȃ��̂������l�X�̎p�����̐S�ۂƂ��ĉ悢���B72�˂̃C�����[�W�����Ƃ��āE�E�E�E�E�E�B�����āA����͂₪�Ă͒N�����o������S�ۂł�����B���́A�����̉f����B���āA�{���ɂ悩�����Ǝv���B2000�N8��1���ɉ����v�m�q����ɏ��߂Ĉ����Ă���A����4�N�̌���������Ă���B����4�N�A�����A�e�X�g�A�V�i���I����A���n�[�T���Ɠ����d�ˁA������2002�N4��25���ɃN�����N�C���A10�����ɃN�����N�A�b�v�A�ҏW�A�A�t���R�A���y����A�_�r���O�ƑS��Ƃ��I�������̂��A2003�N3���ł������B�����̐l�X��1�{�̉f����A�艖�ɂ����č���сA���̒��ɋv�X�ɁA�傫�Ȋ�тƈ��炬���A��݂������ė����B�_�r���O�I���̊ԍہA�Ō�̉��y�ɂ̂��ăG���f�B���O�^�C�g�����f��n�߂�ƁA�����v�m�q�v���f���[�T�[�̖ڂɗ܂��������B ���їz��̐��E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�c�@�Y�g�@�@�i�f��]�_�Ɓj �@���ɋv���Ԃ�ɁA���ъēɉ�����B����15�N7�����{�̂��Ƃł���B �@�V��f��u���Ȃ����āv�̎��ʂ̂��m�点�����������A���̓����̉��ɁA���ъē��킴�킴���s���炨�o�łɂȂ����B �@�u���Ȃ����āv�́A���ъḗA16�N�Ԃ�̐V�삾�Ƃ����B�Ƃ������Ƃ́A�����A����ȏ�̔N�������ڂɂ�����ʂ܂܉߂����Ă����̂��낤�B�v���Ԃ�ɂ��ڂɂ������āA������ƌ��t�ɂȂ�Ȃ��悤�ȉ������������̐S�ɖ������B �@�V��́u���Ȃ����āv�ŕ`���o����Ă����̂́A�܂�����Ȃ����їz�ꂻ�̐l�̐��E�������B�������ē����ł����A�����������їz��̐��E���A�����ɂ������B�����ԁA���ڂɂ������Ă��Ȃ��������A��u�̂����ɏ������悤�Ɋ������B �@���̍�i�́A���s�ʼn������������Ă��鉓���v�m�q����̈˗����āA���ъē��r�{�Ɗē��肪�������̂��ƕ������B�������A����ƌĂт������G����������i�ɂȂ��Ă����B8mm�f�悩��X�^�[�g�������ъḗAATG�i���{�A�[�g�E�V�A�^�[�E�M���h�j�ȂǂŖ{�i�I�Ȍ��f��\���Ȃ�����A�˂Ɏ����I����f�������Ă����Ƃ��̏��S��Y��Ȃ���Ƃł��葱�����A�Ǝ��͎v���Ă���B�����ĕ����ꂽ�v���ɂȂ�Ȃ����Ȃ��̂悤�Ȃ��̂����͔ނ̍�i���犴����葱���Ă����B�����A���ꂪ�A�ǂ������������їz��ʂ̏��Ɗēɂ��Ȃ������̂��Ǝv�����A�����ɂ����ނȂ�ł͂̑��ݗ��R���������̂��Ǝv���B���͊m�łƂ�����i���������їz�ꂪ16�N�Ԃ��f������Ȃ��������ƂɁA�[�����S���o���A����ɐ[������������o�����̂ł������B �@�u���Ȃ����āv�͎����e�[�}�ɂ����f�悾�Ƃ����B������܂��A�����ɂ����їz��炵���e�[�}���Ƃ����邾�낤�B���͎��Ȃ�ɁA���їz�ꂪ�`�����E�́A���s����̐��E�Ȃ̂��A�Ƃ����Ǝv�������Ă����B�����Ύ��́A�ނ��`���G���X�̐��E�i���Ƃ��u�������y���v�u���w�S���v�Ȃǁj�ɋ����̓�����k���A�����邱�ƂƎ��ʂ��Ƃ������ɂƂ炦���Ă��邱�Ƃɕs�v�c�Ȋ������o�����̂ł������B�ǂ����č��їz��́A�������������̂悤�ȋ��n�̓������̂��낤���B���͈��Ղɂ��A���s�̌Â������݂ƁA���їz��́u���v���Ɍ��т��āA���̓��������o�����Ƃ����肵���B �@�u���Ȃ����āv�ł́A���܂��܂Ȑl�����A���܂��܂ȕ��i�̒��Ɍ����B���i�͐l�������̐������Ƃ͖����̂悤�ɐ�捂Ŕ������B�����Ĕނ�́A�u���s����v�Ƃ����ׂ������I���̖������������������Ă���悤�Ɍ�����B �@���їz�ꂪ1960�N�ɋr�{�E�ēE�B�e�ɓ�������8mm�f��u������v�ł́A��l�̒j���͌��Ő�����������^�ё�����B���̉ʂĂ��Ȃ������s�ׂ���A�������͂��܂��܂ȈӖ���ǂݎ�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����A�����ǂݎ��Ȃ����R������������Ƃ��ł��邾�낤�B���͂����ɕ����I�Ȓ��O����������Ă��܂����B�܂�A���s����ł���B �@���э�i�ł́A����s�ׂ̔������A���̂��Ƃ̈Ӗ���ω���������A���邢�͐[���������肵�Ȃ��悤�Ɍ�����B�u���Ȃ����āv�̎Ⴂ�j���͕��������ăL�X���������邪�A���ꂪ�Ӗ��I�ɕω����邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ������Ɏ��ɂ͌������B����́A�u������v�̐Ή^�тƓ����悤�Ȕ����ł���A�J��Ԃ��ł����āA����ɉ������Ӗ���t�^����̂́A���鑤�Ɉς˂���B �@�ނ���A���̍�i�Ŗ��m�Ɍ�����̂́A���y����]�ޘV�l�ɂ��ẴX�P�b�`���낤�B���ъē��g�f�������L�����N�^�[���Ƃ����V�l�́A���ɂ������Ă���B�ḗA���ɖ]�ސl�ԂɁA�Ђ����Ȍ���Ȃ���������������Ă���悤���B �@�����v�m�q�������関�S�l�̐������Y�͑m���ɂ���Ē��O�ւƓ�����Ă����悤�Ɏv����B�����ł��Θb�̔ޕ��ɏ��s���킪������B�@�f��ē���16�N�̋́A���їz��ēɉ��������炵�����B���ɂ́A�f���ƂƂ��ăX�^�[�g�����Ƃ����獂�ъē������Ă������E�ς����������������܂��ꂽ�悤�Ɍ�����B �@����ɂ��Ă��A�Ë��̂Ȃ��A��łȉf���Ƃł���B������̏_�炩���A�����ɂ����s�l�炵�������Ɖ��䂩����������������l�����A���͐c�̋����l�ԂȂ̂��A�ƁA���͎v���B �@�u���Ȃ����āv�ŁA���їz��ḗA���������������Ǝv���Ă������Ƃ����ׂČ��������A�Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���A�Ǝ��͊뜜����B���Ƃ��ẮA�܂���������Ȃ����Ƃ����������āA�܂��f�����肽���Ƃ����C�����ɂȂ��Ă���邱�Ƃ�S����]��ł���̂ł���B ��捂ɕ`�������Ǝ��@�|���їz��ē̐V��w���Ȃ����āx���ςā| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���@�Ëv�F �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����ƁA�f��]�_�ƁA�����|�p��w�����j �@50�N�ȏ���f����������Ă������̂ɂƂ��āA�ŋ߂̍�i�͂₽��ɓ��B�A������d�q�������{�����ڂ܂��邵�����̂������B��75��A�J�f�~�[��6������Ƃ����w�V�J�S�x���ς����A���҂��ē����炵���d�������Ă���̂����A��͂�ڂ܂��邵���ɂ͕ς��͂Ȃ��B���́w���Ȃ����āx�͂��������ߔN�́A�V�N�҂ɂ͊Ⴊ�`�J�`�J����悤�ȁA�������ʂ̖��łɑ傫����Q�̂��̂Ɛ��ɑɂɂ���A���ڂ��ׂ���捂ȏG��ł���B�@���Ƃ��ƍ��ъē�70�N�ォ��80�N��ɂ����Ċ����f���ƁB�����́u���{�A�[�g�V�A�^�[�E�M���h�v���㏂�Ɍ|�p�I�Ȓ�\�Z�̉f������낤�Ƃ����ӗ~�I�ȉf���Ƃ����\���Ƃ��Ύ��������Y�A���R�C�i�A���ؘa�Y�A���z��A�ꐢ��Ⴂ���X�c�F���A��X����Ȃǂ̂Ȃ��ł��A��X�Ƃ��Ȃ������s�o�g�ŁA�Ƃ�킯8�~����16�~���̏��^�f��ʼns�������I�ȉf��������ē��p��\���Ă����B���^�f��̃J�����͒ʏ��35�~���̂��A��莩�R�ɁA����z�V�O�ȓ��������邱�Ƃ��o����B���т�8�~���ł́w������x16�~���ł́w���x�Ȃǂ����ۓI�ɂ������]�����A35�~���ł́w�{�w�E�l�����x�O���R�I�v����́w���t���x�w�������y���x�w���w�S���x�Ȃǂِ̈F��݁A�w��S�����x�ł̓}���n�C�����ۉf��ՃO�����v�����A�w���t���x�͌|�p�I��������b�V�l�܂��Ă���B���ꂪ80�N��Ɂw���V�тق������x���B���Ă���͉��̂��f�悩�牓�������Ă���������A���̍�ɂ�����o���Ă��鏗�D�Ō��c����ɂ��鉓���v�m�q�̋����v���ōĂу��K�z������������̂��B�����̖��O���o���̂ŋL���Ă������A�M�҂����������m�����ٍ̂͐�́w�莆�x�Ƃ����Y�ȂɁA��͂荡�x�̉f��ɂ��o�Ă���l�薛�g����ƂƂ��ɏo�����Ă���Ĉȗ��ŁA�ޏ��́s��l�����̌���E�Z�U���k�t�Ȃ錀�c�����s�ł���A�Ɠ��̕�������ɍ��C�悭�����Ă����B����l�͒m��ЂƂ��m������@�̍��i�ҁB�ޏ��͏@���I�Ȃ��̂ɂ��S������悤�ŁA���̐������ƔS�苭���ɂ͓��������������̂��B���ъē����Ƃł��鐼�w�̑щ����o�ċv���Ԃ�ɎB��C�ɂȂ����̂��A���̉f��̃v���f���[�T�ł����鉓������̈�r�Ȑl���ɂ����̂��낤�B����̂�35�~���ŁA�s���Ɛl�Ԃ̑����t��`�������Ƃ����ē͖{�����݂ɔ����ł������킴�Ǝ����Ŕ������悤�ɂ��āA�J�����͑Ώۂ��Î����ē������Ƃ��Ȃ��B�Ώۂ̉��[���Ђ��މ��������i���̉f��ł͐��Ǝ��ƈ����j���ɂ߁A�݂͂������Ƃ��邩�̂悤�Ɂ[�@���s�A���w���ܘ_�o�Ă��邪�A���{�C�ɓY�������l�Ƃ��̋߂��炵���p������ȕ���B�o�ꂷ���Ȑl���ɂ͌l�����Ȃ��A�V�l�i����O�j��t�i�،��Ƃ��Ђ�j�m�i�I�ˈ��j���S�l�i�����v�m�q�j�j�i�|���c�j���̒��V�i�l�薛�g�j�哹�|�l�i�B�c�M���j�����������i�������\�j�v�i��������j�ȁi���؏t�j���ҁi��{���j�Ⴂ�j�i������j�Ⴂ���i�啽�R���j�ق��ɂ��x���i���c���j�Ō�w�i�đj�Ƃ���������B�ނ��邢�͔ޏ��̊ԂɁA���I�ȂȂ��肪�͂��ɂ���͈̂��y����]�̘V�l�ƁA���̗F�l�ō߂ɂȂ�̂��o��Ŗ]�݂������Ă�낤�Ƃ����t�̓�l���炢�ŁA������o��l���̊Ԃ̌��I�Ȋ������h��ȃh���}����؋N����Ȃ��B���̂����A�J�����͐Â��ɁA���������X�Ȃ܂łɓƂ�ЂƂ�̐l�Ԃƌ����������A���[���ƒǂ������A���̓��ʂ܂ł�\���悤�ɐH������A�����ė������Ƃ��Ȃ��B��捂ȏG��ƌ������̂́A�����̂��Ƃł���B �@�f��͂܂��ŏ��́A�א����̊K�i�⓹���������ƁA������Ȃ����������ǂ�ŕ����Ă����V�l�̕\��ňٗl�ȋC����Y�킹�A�ϋq����C�ɗ��ɂ��Ă��܂��B�w�����āE�E�E�����āE�E�E�������āE�E�E���Ԃ��~�܂�E�E�E����������Ă��A�i�F�͕ς�炸�E�E�E�x�V�l�͂��̌��t�������̂悤�ɌJ��Ԃ��Ȃ���d�����ǂ�ŕ����Ă���̂����V�l�̊Ⴊ�O�E�̉������Ă��Ȃ��̂��B�ł͉������Ă���̂��H�����̂Ȃ��́u���v�̊ϔO���̂��Ă���̂��B���̘V�l�������铡���ɍI���B���s�̌��c���|�̃x�e����������҂Ŏ�Ɏ҂ł����邪�A������������s�́u�l�ԍ��v�ɋq�����Đl�`�t�̈ꐶ��͋����A�����@�ׂɒ���グ�Ă݂����B���x�����̈��y����F�l�̈�t�ɗ��ޘV�l�̓��ʂ�I�m�ɉ����Č������B�J���������̘V�l�̕\��ɐH�����Ĕނ̎�����\���̂Ɠ��l�A�v�������ĔߒQ�ɂ���関�S�l�ɂ��A�{�X�g���o�b�N�Ў�Ɏ��ꏊ�����߂Ă��܂���Ă��钆�N�j�ɂ��A�p���ɓ������Ȃ������̒��V�ɂ��A���̕\��Ƃ������J�����i�u���V�тق������v�́A�Ƃ������������j�͈�甍���������ɐN�����悤�Ƃ���B����́A���̃V�������A���Y���̒����ƃW���R���b�e�B��1956�N�Ɂu���F�j�`�@�̏��V�v�삵���܂�Ɂu�������ƁA�����Ɍ������Ăǂ��܂ł������Ă������ƁA�����ĉ����c�邩���悤�v�Ɛ錾���ٗl�ȏ����������肠�����悤�ɁB�p�������ɐG�ꂽ���̂ɂ͂����ɉf�扻�����ꂽ�����w�p�s�x�����������A���̍�i�̓��F�̓X�C�X����̒����Ƃ̌��t������ɉ�������ӗ~��Ǝ���悤�ɂ��v���B�@�V�l�A�ЂƑ����ƂɁw�n���A�Ɋy�A�n���A�Ɋy�x�ƙꂫ�Ȃ���A�Ō�͊C�݂���C�ɐg�𓊂���{�X�g���o�b�N�̒j�A�w��������A���������ďo�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�x�Ɠs��̕a�@�֓����Ă������炵���N�Ȃǂ̎����Ƃ݂�Δp���̒��V�Ɂw�����Ղ�͏\�N���O�ɏI�������x�ƌ����Ȃ�������l�̐_�Ђ̋����Łs���܂̖�����t�����Â����ҁA���Ɋ������������Ⴂ�j���͐��̎����Ƃ����Ƃ��납�B�����͌�����ς���t�����m��Ȃ��B�B�ς��������m�i�I�˂��u����ݍ��v�ɂ��ĕM�҂Ƃ͋��m�����A�V��g�̓y�����e���r�ł���Ă���L���ɂȂ������A�ŋ߂Ƃ݂ɕ��i����������j�͕ʂɂ��Ă��̒��Ԃɂ���̂��w�������������݂Ă���悤�x�ƈ����݂����ݒ��߂関�S�l�A�}���V�����̃��[���̐S�z������v�w�A�����������ȂǂȂǂł��낤�B�������A�n�߂Ɍ������悤�ɁA�����̐l�X�͗Ⴆ�C���X�^���[�V�����̂悤�ɑ����ɔz�u����Ă��邾���ŁA�ʑ��I�ȈӖ��Ō��I�ɗ��݂������Ƃ͂Ȃ��B����ł��āA�W���R���b�e�B���������[���Ӗ��ŕv��v��̓����ɑ��݂��鉽�����\�����I�Ɍ����Ă����̂������B���X�g�ŊC�ɒ��ޑ傫�ȐԂ����z��w�i�Ɉ���������҂����̂����Â��Œ��߂��������̂́A���Ɨׂ肠�킹�����̎�����`���ĂȂ��A�ē��҂��]���ւ̊�]�ł��낤���B�t�L���Ă��������ъē̂��D���ȉf��̓A�����E���l�́w���N�}���G���o�[�h�Łx�Ɠ��{�f��ł͏��È���Y�́w��������x�����������A�����v���Ă��̐V����ς�ΐ�����Ɣ[���������������B �E�E�E�E���їz��I�Ȃ���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������j�@�i�f��]�_�Ɓj �@�v���Ԃ�̍��їz��ē�i�ł���B�l�f��̏o�g�ł���߂Č��I�ȍ�i�\���Â��Ă����f���Ƃ�����A�v���Ԃ肾����Ƃ����Ĉ�����Ȃɂ���\�z���Č��ɍs�����킯�ł͂Ȃ����A�������ς���Ă͂��Ȃ������B�Ƃ������A���̍�i�ł͍�҂͗]�v�ȗv�f���킬�����A�킬�������Ă��ɍ��щf��I�Ȃ���̂̋��ɂ̌`�Ɏ��������̂悤�ɂ����v����B �@�o��l���͂������邪�A�Ƃ��ɒN����l���Ƃ������Ȃ��B���̐l�������̑����͑��݂ɂ��܂�W�Ȃ���ʂɌ���āA�w��Ǒ��ɐl�̂��Ȃ����i�̒����������B���̓o��l���Əo����Č��݂̐S�������Ƃ������Ƃ͂��邪�A�����Ŋ����������ăh���}���i�s����킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ������A�h���}�̐i�s�Ƃ����ʏ�̌��f��̏펯��f�O�����Ƃ���ɂ��̉f��͐��藧���Ă���B�h���}�͉�b�ł���A���݂ɑ���̔�������|��Ƃ��Ď�����i�s���W�����Ă䂭���̂����A���̉f��ł́A������Ⴍ�Ă܂������Ɋ�]�������Ă�����l���m�̃J�b�v���̉�b��ʂƂ��āA�Z���t�͖w��ǓƔ��̂悤�Ȃ��̂ł���B���肪����ꍇ�ł���{�I�ɂ����ŁA����͂����A�����̓Ɣ����m�F���Ă����ؐl�ł���ɂ����Ȃ��悤���B�����Ȃ��Ȃǂƌ����Ɣے�I�Ɏv���邩������Ȃ����A�����ł͂Ȃ��B�����̓Ɣ����m�F���Ă����ؐl������Ƃ������Ƃ͑�Ȃ��ƂŁA���ꂪ���邢�͈��Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B����ȏ�̉ߏ�Ȃ��̂�l�Ԃ�l���ɋ��߂��A�������ꂾ���������ɂ��킾�����A����ȊO�̗v�f�����ɍ�����Ƃ���ɁA����A���щf��I�Ȃ���̂̋��ɂ̌`�������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B �@�܂��ЂƂ�̘V�l������āA�����������炭����ЂƂ�ł���ƕ����B���̍��̔������ɐS������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ނ̓����߂Ă���̂͗F�l�̈�҂�����y�������Ă��炤���Ƃ����ł���B���͂���邱�ƂɊS���������ނ̐S�����A���S�̓Ɣ��Ŕ����������B�����邱�Ƃɖ��S�ɂȂ��Ă��A���̐S�����������邱�Ƃ��ł��邵�A�f��I�ɔ������\���ł���Ƃ������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��낤�B �@�F�l�̈�҂͍���B���邪�V�l�̐\���o���e��悤�Ƃ���B���ۂɂ�������̂��ǂ����͕�����Ȃ��B�Ƃ肠�����A�~�߂��蓦�����肷��̂ł͂Ȃ��A�F�l�̌��t�̕�����Ƃ��Ă��̏ؐl�ɂȂ��������Ȃ̂�������Ȃ��B��]�Ƃ����g���ɂ�����a�h�ɂƂ���ꂽ�l�ԂɁA���������ĉ��҂���ɂ͂��ꂵ���Ȃ��̂�������Ȃ��B �@���邢�́A�ߑa�Ŗw��ǐl�̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������̐_�Ђ̋����ŃK�}�̖�����̌��������Ă���Ⴂ�|�l������B�Ō�̑����炵���H�D���͂������N�y�̒j���A�����Ղ͂Ƃ����ɏI�����̂������߂Ȃ����ƒ������邪�A�����ɂƂ��Ă�����~�߂邱�Ƃ͎��ʂ��ƂƂ��Ȃ����ƌ����Č|�𑱂���B������݂��ɐM�����邢�͐S��������Ă��邾���ő���ɂ͂Ȃɂ��e�����y�ڂ��Ȃ������b�Ƃ�������d�̓Ɣ��ɋ߂��B�����A�e���͋y�ڂ��Ȃ��Ă��A�݂��ɂ������������Ƃ������āA������Ă���鑊�肪�����ɂ����Ƃ������Ƃ͂��������̂Ȃ����Ƃł���B �@���̉f��ł͓o��l�������͊��������Ȃ����O�i�����Ȃ��B�O���ɂ͎����҂��Ă��邾�����ƕ������Ă��邩��ł���B�W�^�o�^�͂��Ȃ��̂��B�����A�����ӎ����Ă�������ċz���ƂƂ̂��悤�Ƃ���҂́A���̋C�����������茩�Ƃǂ��Ă����l�͂��Ăق����B�l�Ԃ̏o�����Ƃ������Ƃ̏d���Ӗ��͂����ɂ���B���їz��́A�l���W�^�o�^����l�q�ɂ��܂�S�͎����Ȃ��B������܂��A�����v���B�����Ĉ��Ƃ́A����v�������L���邱�Ƃł���A����邱�Ƃł���A�~�߂邱�Ƃł���B���̉f��͂��������C���[�W�̏������������߂āA�]�v�Ȃ��͍̂��ɍ���Ă���B�����Ă��ꂾ�����c�����̂��B����͂�����A���їz�ꂪ���Z�Z�N�O��ɏ��^�f������{�̃C���f�B�y���f�B���g�A������A���_�[�E�O���E���h�h�̃G�[�X�Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ���������̎d���̂ЂƂ̗����W�ƌ������i���Ǝv���B�������炠���������I��O�͂����Ŕ��ɐ����̂ƂȂ����B |
| �u���Ȃ����āv���ӏ܂��������܂������X���̊��z�@�@ |
|---|
|
| �|�|�|�����\�����݁E���₢�������|�|�| ��l�����̌���@�Z�U���k ��601-8014�@���s�{���s�s��擌����͐���43�Ԓn Tel/Fax�@075-672-3426 �@e-mail cezanne1983@ybb.ne.jp |